〒530-0015 大阪市北区中崎西2-2-1 東梅田八千代ビル10F
TEL : 06-6363-0506 FAX : 06-6363-0515
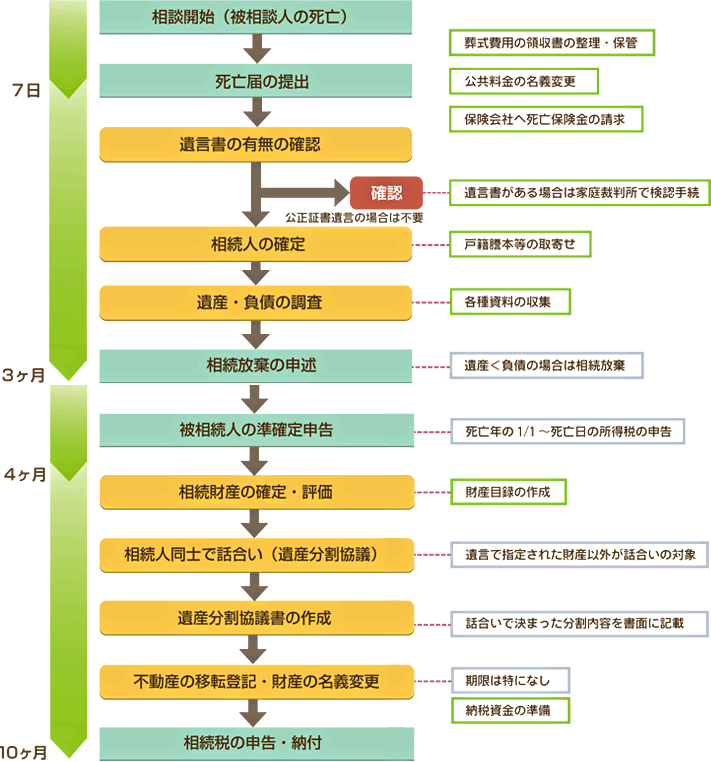
相続税とは、相続という原因によって財産を取得した人に対して国が課税する税金、国税のことです。
相続とは、『人が死亡した場合に、その人が持っていた財産の全てがその人の妻や子など一定の身分関係のある人に受け継がれること』をいい、死亡した人を『被相続人』、財産を受け継ぐ人を『相続人』といいます。
この場合の『財産』とは、必ずしもプラスの財産だけを指すわけではなく、被相続人が生前に借金をしていた場合や、商売上の買掛金を残して死亡した場合などのマイナスの財産もすべて相続人に受継がれます。
相続税は、ある人の死亡により遺産が相続人に受け継がれた時に課税されます。遺産額が大きくなれば税負担も大きくなります。相続税の税負担の軽減を図るためには、生前に妻や子に遺産を贈与して遺産額をゼロ・相続税をゼロとしてしまおうと考えるのが一般的です。しかしそうすると、相続税を納める人がいなくなってしまいます。そこで、『贈与税』という税金で『相続税』を補完する役割を果たしているのです。
相続税を少なくするために生前贈与を多くすると贈与税の負担が重くなります。
一方、贈与を一切行わない場合はその分だけ相続税の負担が重くなります。
この関係が、贈与税が相続税の補完税と呼ばれるゆえんです。
相続税は原則として個人に対して課税されます。
例外的に、人格のない社団等(PTA、町内会など)や持分の定めのない法人(一般社団法人、一般財団法人など)が遺贈によって財産を取得した場合は課税されることがあります。
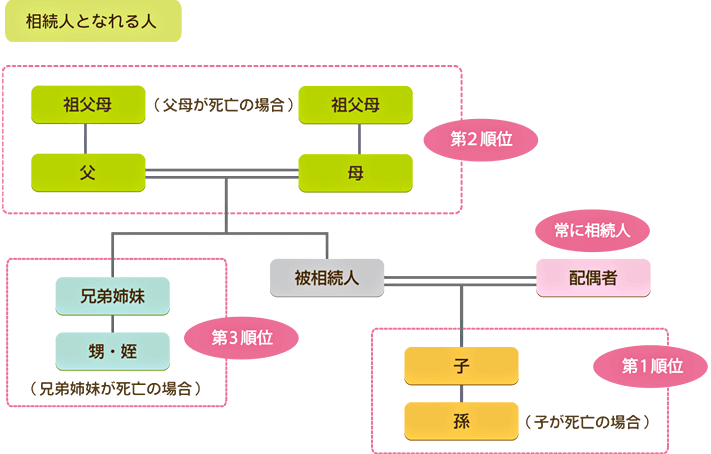
被相続人が死亡した場合、誰がその遺産を受け継ぐことができるか(=相続人になれる人は誰か)については、民法上の『法定相続制度』として定められています。
民法では遺産を巡るトラブルを出来るだけ少なくするために、相続人となれる人を次のように区分しています。
① 血族相続人・・・被相続人と血がつながっていることにより相続権が認められる人
② 配偶相続人・・・配偶関係があったことにより相続人となる人
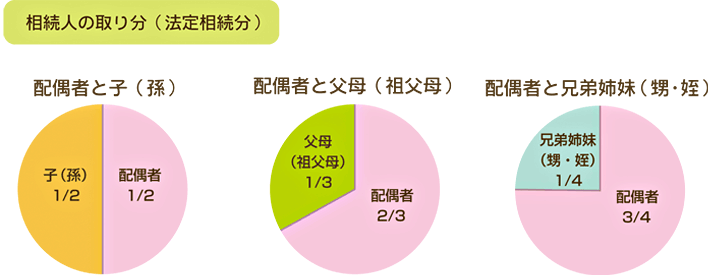
相続人が複数いる場合のそれぞれの相続人の遺産の承継割合を相続分といいます。
本来の相続財産とは、具体的に次のものが挙げられます。
①土地・・・田、畑、宅地、山林など
②土地の上に存する権利・・・宅地の地上権、借地権など
③家屋・・・自用の家屋、貸家、工場、倉庫、駐車場など
④事業用財産・・・売掛金、貸付金、商品、設備など
⑤有価証券・・・株式、出資、公債、社債、証券投資信託など
⑥現金・預貯金・・・現金、普通預金、定期預金、当座預金など
⑦家庭用財産・・・家具、書画骨とう品、宝石など
⑧その他の財産・・・自動車、ゴルフ会員権など
みなし相続財産とは、具体的に次のものが挙げられます。
①生命保険金
②死亡退職金
相続や遺贈によって取得した財産で、金銭的な価値のあるものはすべて相続税が課税されるのが原則です。
しかし、財産の種類や性質によっては国民の感情面や社会的政策的な面から課税するのが適当でないと考えられるものがあります。相続税法では、具体的に次の7種類が非課税財産として規定されています。
①皇室経済法の規定により、皇嗣が承継する物
②墓所、霊びょう、祭具など
③一定要件に該当する公益事業者が取得した公益事業用財産
④心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権
⑤相続人の取得した生命保険金等で法定相続人1人当たり500万円で計算した金額
⑥相続人の取得した死亡保険金等で法定相続人1人当たり500万円で計算した金額
⑦相続財産を国や公益社団法人等に寄付した場合の寄与財産
相続では相続の放棄をしない限り、被相続人の生前における借金などの債務も相続人に承継されます。相続税の課税上は、実際の手取財産を計算するためにこれらの債務を控除する必要があります。これを債務控除といいます。債務控除の対象となるものは、具体的に次のものが挙げられます。
①被相続人の債務(未納の所得税、住民税、固定資産税などを含みます。)
②被相続人に係る葬式費用(香典返しの費用は葬式費用に含まれません。)
(※)領収証の取れない費用は、出納メモなどでこまめに支出金額を書き留める様にしましょう。
相続税は、死亡した人の財産(遺産)に対して課税されます。
相続税が課税される最低ライン(基礎控除額)は、『5,000万円+1,000万円×相続人の数』で計算した金額になります。 例えば、相続人が1人の場合は基礎控除額が6,000万円、相続人が2人の場合は基礎控除額が7,000万円となり、相続人が1人増えるごとに1,000万円ずつ加算される仕組みになっています。
相続人3人(妻と子供2人)の家庭では基礎控除額が8,000万円(=5,000万円+1,000万円×3人)となりますので、遺産総額 がこの8,000万円を超える場合には、相続税の課税問題が出てくることになります。